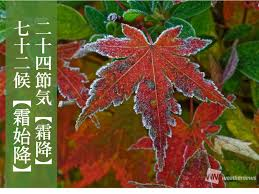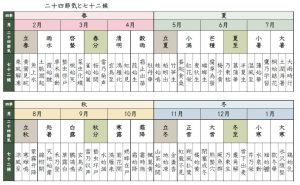~ 二十四節気・七十二候が教えてくれる、時の整え方~
「時(とき)を味方につける」。
これは、経営者にとって最も静かで強い武器です。
現代のビジネスは、年次・月次・週次の数字で回っています。
しかし、日本にはもう一つ、自然の呼吸に沿った暦があります。
―それが、二十四節気・七十二候です。
季節のリズムをビジネスに取り入れる
日本には、1年を24の節目に分ける「二十四節気」と、さらにそれを72に細分化した
「七十二候」という暦があります。
これらは、自然の微細な変化を捉え、農作業や生活の指針として活用されてきました。
季節に寄り添うスケジュールは、心と組織の呼吸を整える
たとえば「立春」。春といってもまだ寒い。
でも、陽が少しずつ長くなっていくその気配を感じると、
「この時期こそ、仕込みどき」と思えるようになります。
「立夏」は、夏の始まりを告げる節気であり、
ビジネスにおいても新たなプロジェクトのスタートや、組織の活性化を図る良い機会と捉えることができます。
「寒露」は空気が澄み、頭も心も引き締まる節目。来期に向けた構想を描くには、こうした季節が合うのです。
こうして節気のリズムに沿ってスケジュールを組むと、会議にも、現場にも、自然な張りとゆとりが生まれるようになります。
予定を“詰める”のではなく、“整える”という感覚”
――これが、季節の力です。
マーケティングにも「候」の視点を
「七十二候」は、約5日ごとに訪れる季節のメッセージ。
たとえば…
・蛙始鳴(かわずはじめてなく)(5月初旬):命の声が戻ってくる。
→ 新サービスの発表や、理念を語る動画発信に最適。
霜始降(しもはじめてふる)(10月下旬):冷気が満ち、年の瀬が近づく。
→ 一年の締めくくりに感謝を伝える、特別便りや顧客対話の時期。
「時期の言葉」に合わせて発信することで、顧客の感性に静かに届くマーケティングが可能になります。
商品より“空気感”が選ばれる時代には、こうした視点が大切です。
経営は“自然”から学べる
昔の日本人は、作物の育ち方、風の動き、鳥の声から、生き方を学びました。
ビジネスにも、それは通じています。
自然の変化に耳を澄ませると、
焦らずとも「いま手を打つこと」「いま手放すこと」が見えてくる。
そして、社員もまた自然の一部。
リズムを整えることで、働き方の質も、人間関係も、ふんわりとほぐれていくのです。
数字で管理する経営だけでは行き詰まる時代。
今こそ、感覚と季節を取り戻す時です。
経営者の暦に「ゆとり」と「潤い」を
数字ばかり追いかけていると、時間の流れは硬く乾いていきます。
しかし、風や光に目を向けると、スケジュールにもやさしい呼吸が生まれます。
毎日、仕事のスケジュールに追われるだけでなく、自然の呼吸に沿った暦を取り入れ、心に「ゆとり」と「潤い」を取り戻したいものです。